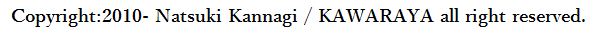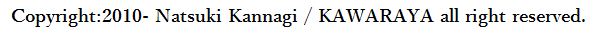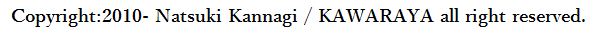モニ・ヒューマンの憂鬱
一
モニ・ヒューマン。
いつからそのモニ・ヒューマンが観測されるようになったのかは定かではないが、少なくとも人間が今の文明を築き上げたころにはすでにモニ・ヒューマンは実在していたといわれている。
モニ・ヒューマンの名前の由来はいたってシンプル。その外見を二つの単語で表したものである。
モニターとヒューマン。つまり、頭がモニターになっている人間ということだ。
それ以外は人間とまったく変わっていない。だからモニ・ヒューマンを人間と取るか、彼ら独特のカテゴリーとするかは、人によって判断が変わってしまう。
そんなモニ・ヒューマンは人間の恋愛対象になりえないことが多い。やはりモニター型の頭がネックになっているのだろう。それをモニ・ヒューマン側が思っているのか、人間が思っているのかは解らないが。
しかしながら、モニ・ヒューマンだって恋愛をする自由もあるだろう。
これは、私の友人であるモニ・ヒューマンを追ったある一つの思い出話になる。少々追えていない部分もあるかもしれないが、それは少し我慢してくれたまえ。そうしてくれると、私も非常に助かる。
二
「一つ、聞きたいのだが」
国立大学の図書館。荘厳な雰囲気を漂わせ、一言も発する状況を許されていないような、そんな環境で、私は声をかけられた。
顔を上げると、そこに立っていたのは、モニターの頭にセーター、マフラーを巻いている男だった。――モニ・ヒューマンというやつだ。
「君は、モニ・ヒューマンかい?」
「だったらどうする?」
ニヒルな笑みを浮かべるモニ・ヒューマン。モニ・ヒューマンは文字通り、ニヒルな笑みを浮かべることができる。それだけではなく、人間に負けない豊富な表情を表現することができる。そもそも人間の脳だって電気信号でやり取りしているのだから、それが出来ないことは無い。
モニ・ヒューマンは電気信号で頭部のモニターに感情を映し出す。すなわち、モニ・ヒューマンは人間以上の感受性に富んだ生き物であるといわれているのだ。
まあ、そんなことはどうだっていい。私は彼のニヒルな笑みをどうにかしてさえぎろうとすべく、会話を続けることとした。
「……別に何でもないよ。ただ、モニ・ヒューマンをこの大学で見るのは珍しいから言った。ただそれだけのことだ」
「ああ。そうかもしれないね。確かにモニ・ヒューマンは僕しか居ないかもしれない。そして、モニ・ヒューマンはこの近辺に住んでいないし」
「そこまで言うなら……、どうしてここに通うようになったんだ? ここはそこまで素晴らしいものも無いと思うが……」
「哲学をまなびたくてね。それで有名な滝谷教授の研究室に居るわけだ」
「滝谷教授、だと? あの偏屈で有名な」
滝谷教授は確かに哲学では有名だ。マリーの部屋やポールワイス、そういう感じの思想実験? というものについての論文をいくつも書いているらしい。らしい、と最後を締めているのは哲学という分野について、あまりにも自分が解らないだけのことだ。だから、ざっくばらんに言うしか無いということになる。
滝谷教授はあまり研究室に人を入れない。そんなことも聞いたことがある。どうしてかは知らないが、たぶん彼の性格が合わないのだろう。研究室に入る人間は居ないことは無いが、そう長く持たない。それが、彼を人から遠ざけている原因なのかもしれない。
「そう。その滝谷教授だよ。……偏屈という人が多いかもしれないが、滝谷教授は話すととても面白い人だよ。素晴らしい人だと言ってもいい。天才だ、まさしく」
「そりゃ……大学教授になっているくらいだからな。それなりに頭はいいのだろうよ」
「確かに」
そう言って、僕は勉強を再開する。ノートと参考書に視線を行き来させて、勉強を始める。どういう勉強をしているのかというのは、まあ、簡単に言えば『試験勉強』になるのだけれど、これについては割愛させてもらうことにしよう。それがいい。そういうほうがいい。
……そのあと、モニ・ヒューマンと何を話したかと言えば、まあ、他愛もない話ばかりだった。あまりに他愛も無さ過ぎて覚えていないくらい。しいて言うならば、彼の名前がユウキという名前だったくらいか。さすがに苗字までは教えてもらえなかったが、別にそこまで教えてもらう必要も無い。
三
それから、何だかんだで僕とユウキは友人になった。出会ったら挨拶をするし、会話もする。ソーシャルネットワーキングサービスで連絡を取ることもあるし、一緒に昼食をするようにもなった。周りからはモニ・ヒューマンとかかわるなんてお前らしいなどと言われたが、正直どうしてそういわれるのかは解らなかった。
なぜなら彼は普通の人間だったからだ。そりゃ、頭がモニターという人間とはまったく違うポイントが一つある。けれど、けれどだ。それ以外の考え方や身体は人間とまったく変わらない。だのに、どうしてモニ・ヒューマンは嫌われてしまうのか。それは社会問題にもなっていることだけれど、しかしながら、それをどうにか解決しようという人間は一握りに過ぎない。国もどうにかしてモニ・ヒューマンを庇護しようといろいろな政策を考えているらしいが、あんまりモニ・ヒューマンばかり庇護していると、今度は普通の人間から批判されてしまう。だから、どちらにも批判されない最善のラインを見極める必要があるということだ。まあ、政治に詳しくない僕が精いっぱいの知識で何とか語ることの出来るものはここまでになる。
そんな彼が昼休み、学生食堂にやってきた。別段それは珍しいことではないし、彼がエネルギー触媒を持っていることも――モニ・ヒューマンは口を持たない。だから、エネルギーを摂取するのも頭部のモニターの横側にあるプラグから摂取する。もちろん人間のするような食事ではなく、電気エネルギーがたっぷり詰まった触媒だ――それはまったく珍しいことじゃない。
ただ、彼がどこか悲しげな表情を浮かべていたこと――それが少し気になっていた。
「……どうかしたのか? 何か、悲しいことでもあったような気がするが……」
「悲しいことがあったわけではないよ。ただ、ちょっとね……」
「何があったんだ? もし可能なら、僕に話してみるのはどうだ? 誰かに話すことで、ちょっとは気分が楽になるかもしれないぞ。まあ、別に強制する必要はないが。言いたくないのであれば言わなくていい」
「……実はさ」
僕の隣に行ってユウキはぽつりとこう言った。
「――好きな人が居るのだけれど」
◇◇◇
ユウキからの言葉を要約するとこうだ。
ユウキは哲学の授業を受けている。もちろん、哲学を専攻しているのだからそれを受けることについては何ら難しいことじゃない。むしろ基本ともいえることだ。
先頭でいつものように講義を聞いていたら、彼の隣に一人の少女が腰かけてきた。
「ねえ、君、いつも先頭で聞いているよね」
講義終わり、彼は声をかけられたのだという。いつもはそんなこと無かったので驚いてしまったらしいので、まともな返事をすることも出来なかったのだという。
だが、彼女はそれでも気にする様子はなく、
「あ、友達が呼んでいるから、またね。君、いつもこの講義を取っているのだよね? だったら、また会えるね!」
そう言ってそそくさと去って行ったらしい。
それを見た彼は、暫く彼女の姿を見守ることしかできなかった。
◇◇◇
「要するに、アレか。一目ぼれというやつ」
「……そうなのかもしれないね」
エネルギー触媒をプラグに差し込み、目を細める。もちろんそのしぐさも映像としてモニターから出力されているので実際にそう表示されているわけではないのだが。
僕はカレーを一口頬張って、噛んで、飲み込む。そして、彼の話に答える。
「だったら、彼女の連絡先なりなんなり聞けばいいじゃないか。名前とか。それがベストかな。名前を聞いて、そこからうまい具合に発展させていく。それがいいんじゃないのか」
そう言っている僕だが、残念なことに彼女のいた経験が無い。いわゆる彼女いない歴=年齢のカテゴリーに所属する人間なので、ユウキにこうアドバイスできる権利ははっきり言って持っちゃいない。けれど、彼が気にしているのだから、アドバイスの一つくらいしてみたくなる。
ユウキは首を横に振って、
「実は名前も知らないんだ。残念なことに。毎回講義で会う時には挨拶を交わすのだけれどね……」
「その時に、名前は知らないのか? というか、出席確認があるじゃないか。あの時に苗字くらい確認できないのか?」
「さすがに苗字は解るよ。……上倉さん、だったかな。とてもカワイイ子だよ。いつもパーカーを着ているんだ」
上倉、か。
聞いたことがあるような無いような名前だ。僕もそこまで人の名前を覚えるのが得意ではないので、人のことを言えないのだけれど。……まあ、いいか。今度、彼に聞いてみることにしよう。
「で? ユウキはどうしたいわけ」
「どうしたい、って?」
「告白して、付き合いたいのか。それとも良き友人として今の関係を持続していきたいのか。どちらかだろ。男と女がどうなるか、って言えば。まあ、僕だってあわよくば前者まで行きつけばいいな、という感じで淡い期待を抱くけれど」
「ええっ? ……うーん、どっちだろう」
どっちだろう、とはどういうことなんだ?
僕はユウキの発言を聞いて思わず首を傾げそうになったが、あんまりそれを外に出すのも彼に悪いし、一先ずそこで止まることにした。
「……なんというか、不安なんだよ。モニ・ヒューマンはまだ、そこまで市民権を得ていない。確かに政府が庇護する法案をいろいろと出して可決されている。それでも人々の心にはまだモニ・ヒューマンを認めない心がある。それは、紛れもない事実だ。そうだろう?」
「そりゃあ、まあ……。でも、もしかしたら、の話だろ? だったら同じ理屈で言えるじゃないか。『上倉さんはモニ・ヒューマンを嫌っていないのではないか』って仮説を立てることが出来る」
そうかあ、と納得した様子に見えるユウキだったけれど、どこかまだしこりが残っているように見える。なぜなら彼は笑っていなかったからだ。笑っていなければ、どこか違和感を抱いている――そう思えたからだ。
一先ず、その相手――上倉さんについて僕のほうからも調べてみることにしよう。僕はそう思いながらカレーの残りをスプーンで掬い始めた。
続きは2016年3月頒布予定の「異種ラブアンソロ」にてお楽しみください!