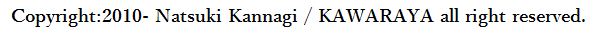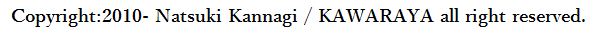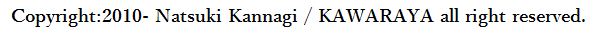10. 金谷くんと節分
「僕に鬼になってくれ、って?」
「お願い! 雄太がどうしてもあなたと遊びたいと言い出して……」
二月三日の夕方、帰り道で私は唐突にそう言った。はっきり言って、唐突にそういうのは申し訳ないと思っている。けれど、こればっかりは仕方がない。あまり学校で私たちは仲良くしようと思っていないからだ。
金谷くんは小さな溜息を吐いて、
「……まあ、別にいいけれど。取り敢えず、鬼になればいいんだね? 節分の準備ってもうできているの?」
「そこは任せておいて! もう既に完璧よ!」
「そうかい。だったらいいのだけれど」
元来私はずっと鬼をし続けてきていたわけだけれど、そろそろ飽き飽きしてきたところだった。だってずっと豆を投げ続けられるのよ? 正直困るの。パーカーの中に豆が入ってしまうし、しばらくは鬼のお面を外しても投げ続けるし(さすがにそこは怒るけれど)。
私の家に着いて、靴を脱ぐ。
リビングに行くと、既に目をキラキラ輝かせている雄太の姿があった。豆の袋を見て、目を輝かせているその姿は、恵方巻を食べることよりも豆を投げることに喜びを感じているようにも見える。……そんなことは無いと思うけれど。
「あ、マキ。おかえりなさい」
雄太の隣にいるのは私の母だ。
「どうも、お邪魔します」
そう言えば金谷くんと母は初めての邂逅だった。
「あらー、あなたが金谷くん? よく娘が夕食で話をしているのよね。あらあらまあまあ、こんな子だなんて知らなかったわ。どうしてもっと早く母に会わせないのよ、マキ」
「……別にいいじゃない。というか、その腕の動き、やめたほうがいいと思うよ。金谷くんが若干引いているし」
「あらあら! ごめんなさいね」
そう言って母は動きを止める。ちなみに既に恵方巻が人数分用意されている。その数は三つ。
……あれ、四つ?
「四つになっているけれど?」
「うん? 何か間違いでもあったかしら。全然解らないのだけれど」
「……ああ、もしかして、金谷くんの分?」
「そうそう」
母はそう言っていったんキッチンに向かった。
「ねえねえ、いつになったら豆まき出来るの!」
升を持った雄太が私に質問を投げる。
「もうちょっとしてからね」
「あの……恵方巻、僕も食べていいのか?」
「もちろん。そのためにあなたをここに呼んだのだから」
「……そうか」
あれ、何か納得行っていない?
豆まきの鬼になるから、十分すぎる報酬だと思ったのだけれど、足りなかったのかなあ。
「よし。雄太、豆まきは、夜にやるんだぞ。まだまだ夕方だからね」
「うん!」
そう言って雄太は頷くと、素直に升を炬燵の上に置いた。
……普段もそこまで素直にいてくれれば、とても便利なのだけれどなあ。
そして既に炬燵に入っている雄太と金谷くんを見て、私もまた炬燵の中に入った。
(ちょっと続く)
TOP