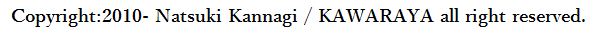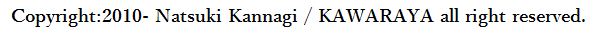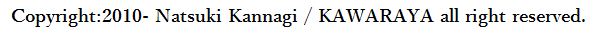13. 金谷くんとバレンタイン2
「ねえ、金谷くん。これ、食べてもらえるかしら?」
私は金谷くんを家に呼んで、ザッハトルテを差し出した。
最初、それが何であるかすぐに理解できなかったようだけれど、ケーキの主成分がチョコレートだということに気付いて、首を傾げる。
「これは?」
「チョコレートケーキよ。名前はザッハトルテ。ああ、もしかしてそこから説明する必要があるかしら?」
「いや、そういうことではなくて……」
どうやら困惑しているようだった。
まあ、当然と言えば当然なのかも。
急に家に呼び出されて、ケーキが出される。しかもチョコレート味。バレンタインとはまず思わないかもしれない。普段はケーキじゃなくて、袋のお菓子だし。
「いただきます」
金谷くんは目をつぶり、手を合わせて小さく頭を下げると、フォークを手に取った。
ザッハトルテを一口大に切り分けてそのままそれを口に入れた。
口に入れて少しして、目を見開く金谷くん。
「……美味しい。もしかしてこれって、駅前のケーキ屋さん?」
「駅前っていっぱいケーキ屋さんがあるから、特定できないけれど」
「ワスレナグサがお店の名前になっている、」
「そうそう。そこのケーキ。店長のオススメなんだって。ちょうどあったから、買ってきちゃった」
「ふうん。成る程。なかなか美味しいね。さすがは店長が進めるだけのことはある。あのひと、昔はなんでも料理を作ることの出来る天才シェフのもとで修業していた、って聞いたことがあるよ。だから、味はピカイチだって」
「へえ、そうなんだ。どうして知っているの?」
「どこかのインタビューで見たことがあるよ。店長のさわやかな笑顔とともにそんな経歴が描かれていたっけ。かなり努力家なんだな、って親が言ったことを覚えているから、なぜかそこだけ鮮明に覚えているよ」
「ふーん……。確かにあそこのケーキは美味しいものね……」
そう言って私は一口ザッハトルテを食べる。
ちょっと大きすぎちゃったので、落ちる前に慌てて口に頬張った。
「あ、ついているよ」
そう言って金谷くんはごく自然に――私の口についていたチョコレートを取った。
「あ……」
「うん? どうかしたの?」
そしてそのチョコレートを――まったく気にしない感じで、そのまま口に運んだ。
「……どうしたの、そんなに顔を真っ赤にさせて」
「え……ええ?」
頬を触る。確かに私の顔はとても熱かった。風邪をひいているみたいに、熱かった。理由は解っている。まぎれもなく、彼は天然で、そういうしぐさをしたのだった。
……なんというか、恥ずかしがっている私のほうが間違っているような、そんな雰囲気。
「別に、なんでもないわよ」
それだけを言って、頬を膨らませて私はザッハトルテを食べ始める。
困惑している様子の金谷くんは、どうやらまだ私がなぜ怒っているのか解っていないようだったけれど。
TOP